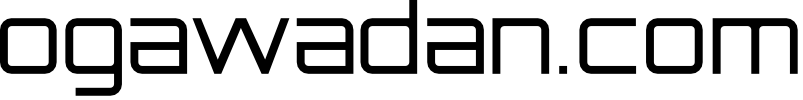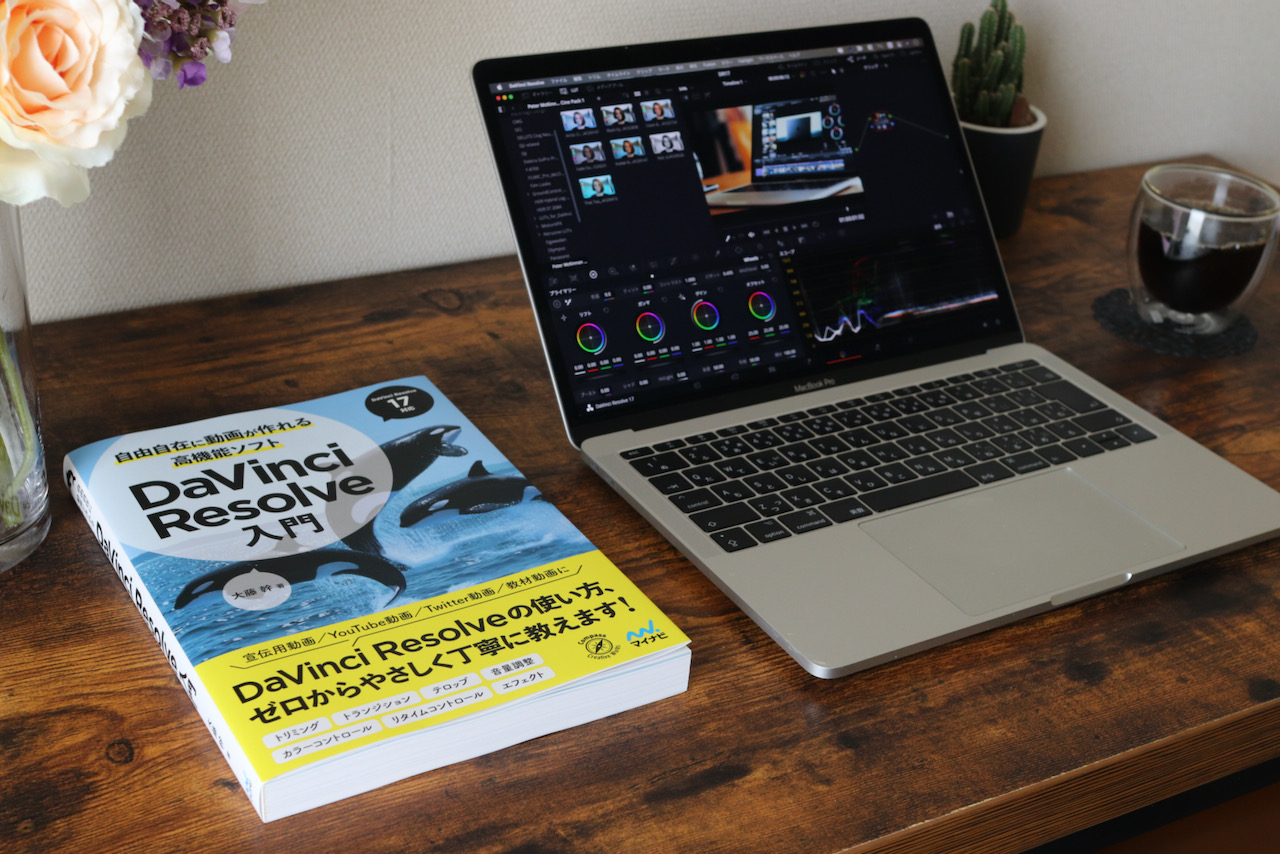イタロ・カルヴィーノの作品をネオ・レアリズモ文学、パルチザン戦争などの視点だけで理解できないことは言うまでもない。そもそもネオ・レアリズモよりもマジック・リアリズムに近く、戦争や革命なども挿入話の一つに過ぎない。
カルヴィーノの作品にはいつも長大な時間が流れている。本書でも革命や封建的/牧歌的な世界の凋落が描かれるが、彼が描こうとしたのはそうしたうつりゆく世界の方ではなく、すべてが過ぎ去ったあと、あるいはすべてがやってくる前に根底に存在する普遍的な世界の方にあった。そしてカルヴィーノは自然に対して普遍性を見出していたように思う。
イタリアの男爵家の長子コジモ少年は、12歳のある日、カタツムリ料理を拒否して木に登った。以来、恋も冒険も革命もすべてが樹上という、奇想天外にして痛快無比なファンタジーが繰り広げられる。笑いの中に、俗なるものが諷刺され、失われた自然への郷愁が語られるカルヴィーノ文学の代表作。(あらすじ)
なぜコジモは木に登ったのか?
このような団体生活に常にコジモが示して来た情熱が、いったいどのようにして彼の人間社会からの絶えざる逃走と和解できるのか、わたしにはまったく理解できなかったが(中略)彼が胸中にいだいていたのは、全世界的な社会という思想だった(264-265)
彼の考えていたことは、もっと別なこと、なにかしらいっさいを包含するようなもので、これをことばで告げることができず、ただあのように生きることによってしか、彼は語ることができなかったのだ。あのように冷酷なまでに、死ぬまで自己を貫くことによって、初めて彼は万人のためになにものかを与えることができたのだ(297)
コジモの弟によれば、コジモが体現していたのは「全世界的な社会」であり「なにかしらいっさいを包含するようなもの」であった。
魚の鰓にでもなってしまったみたいな生活の形体
カルヴィーノの作品は全般的に「寓話」という呼び方がしっくりくる。なのにふと詩的なフレーズが挿入されるところにカルヴィーノの独特の感性を感じる。
しじゅう樹皮に接していて、鳥の羽根の動きや、獣の毛布や鱗、あるいは世界のこうした相貌の表わすさまざまな色の諧調、さらには葉脈のなかをまるで別世界の血液のように循環している緑の流れに、じっと目をそそいでいるという、こんな人間ばなれのした、まるで木の幹か、しゃこの嘴、あるいは魚の鰓にでもなってしまったみたいな生活の形体、こんなにまで奥深く、そのとばぐちまではいりこんでしまった野生の世界――(107)
例えば、「まるで木の幹か、しゃこの嘴、あるいは魚の鰓にでもなってしまったみたいな生活の形体」という表現などにカルヴィーノらしいなまなましさを感じる。普通の人の目では見えない倍率に存在する世界があるようで驚異を覚える。
そして本の終わり方がまた奇妙だけど絶妙な余韻を残す(ネタバレ注意)。
オンブローザはもうないのだ。(中略)まるでわたしがページからページへ走らせたまま、削除や割り込みや、神経質ななぐり書きや染みや空間でいっぱいになっている、このインクの行列に似ている。(中略)身をくねらせたり、枝分かれしたりして、どんどんと走り続け、また解れ、そしてことばや思想や夢の最後の馬鹿げた一房を生らして、おしまいになるのだ(301-302)
イデオロギーの存在する現実世界はコジモとともに消滅し、普遍的なもの――具体的には自然だと思う――だけが後に残る、ということをカルヴィーノは描いたのだと思った。
訳者解説では『われわれの祖先』三部作を構成する作品の一つ、《ネオ・レアリズモ》文学、パルチザン戦争…という視点から分析されるが、この作品を読んでいずれも思い当たらなかった。個人的にはカルヴィーノの短編集『マルコヴァルド、もしくは都市の四季』に近く、素朴な自然に包まれている世界の暖かさを感じた。
訳者解説で参考になったのは、カルヴィーノがキューバのサンティアゴ・デ・ラス・ベガスに生まれたこと、トリノ大学卒業の論文のテーマがコンラッドについてだったことの2点のみ。