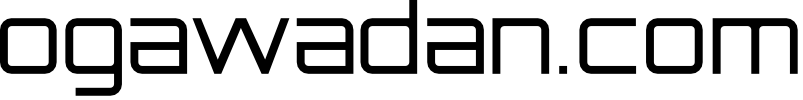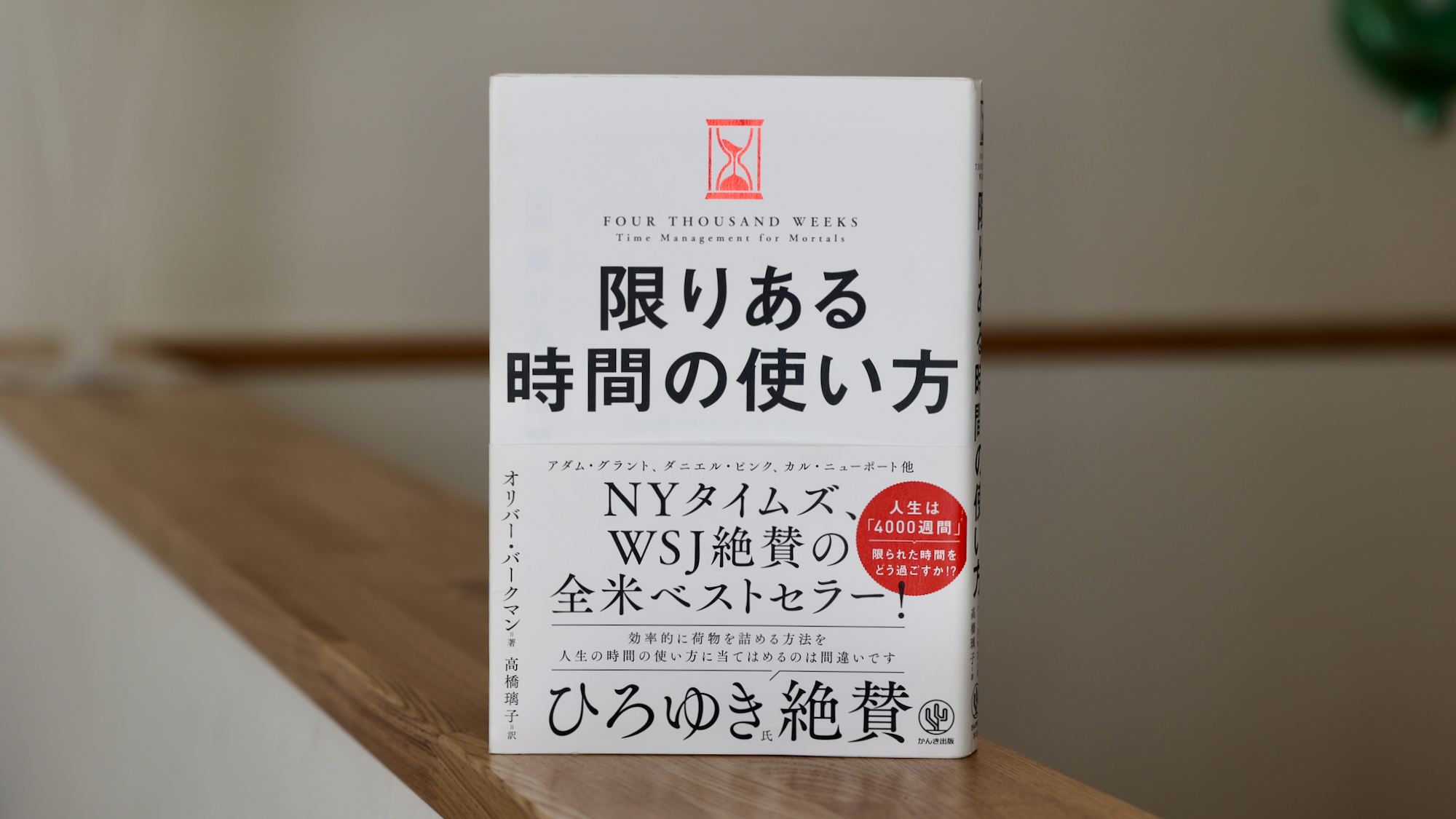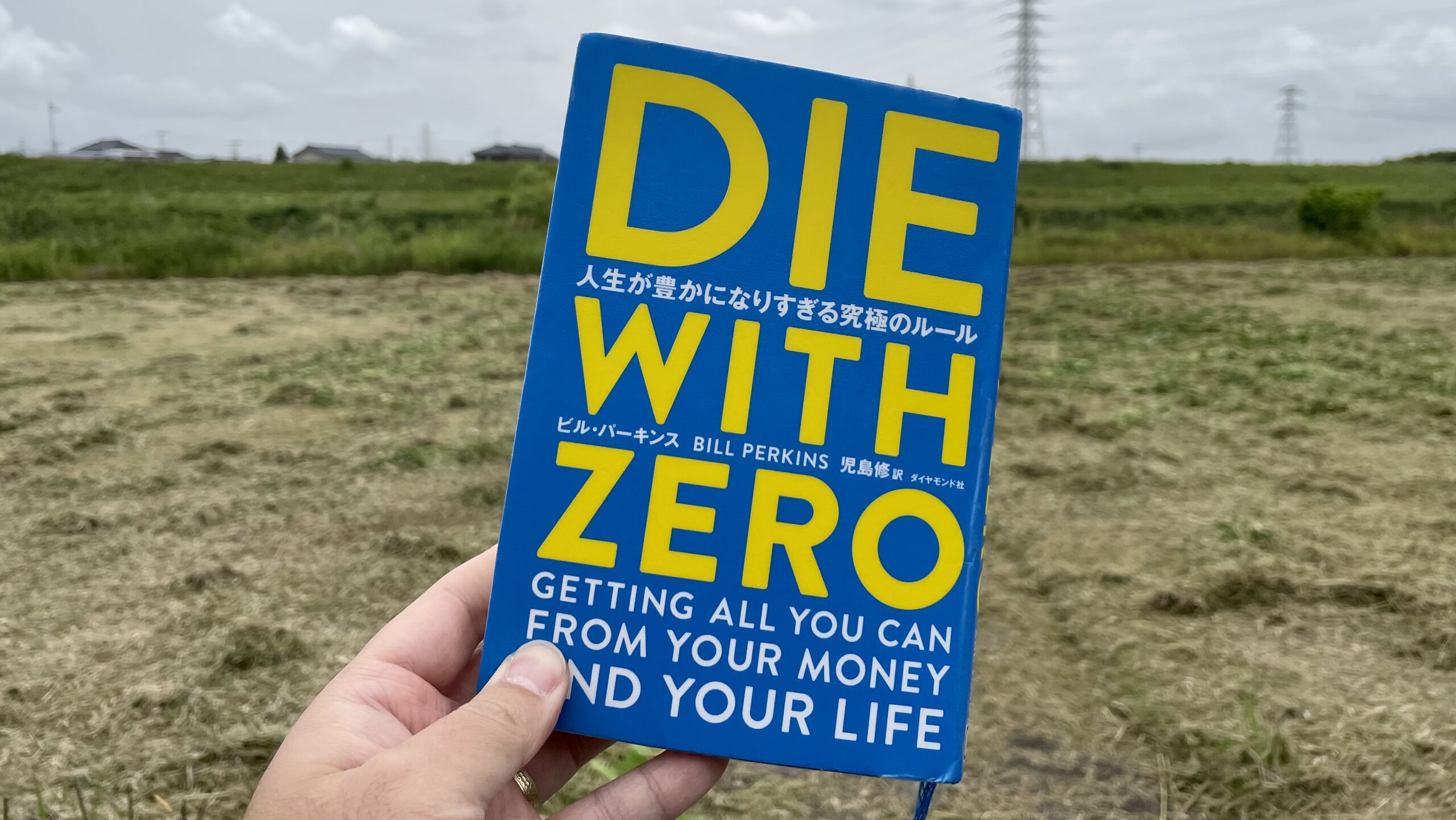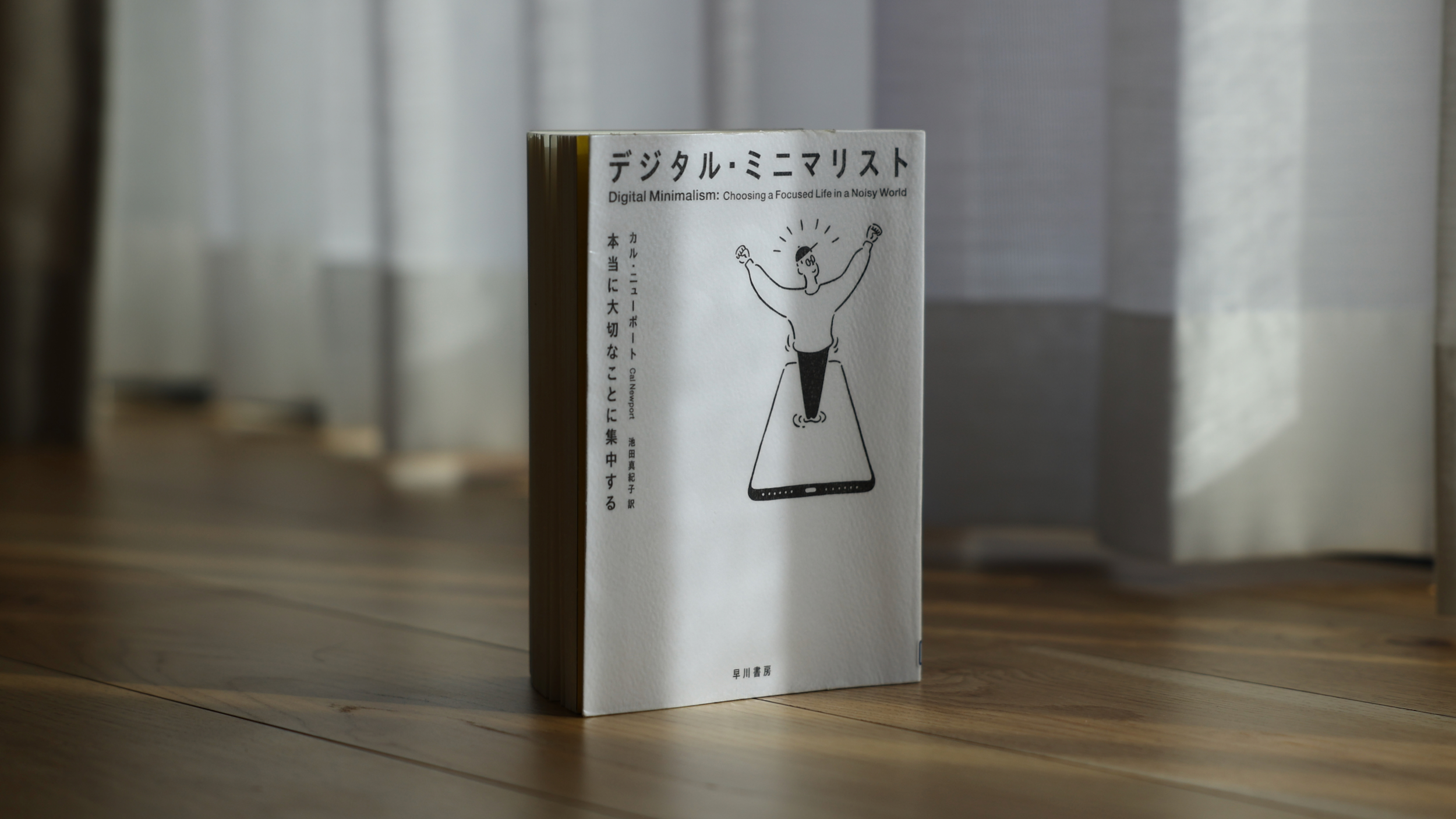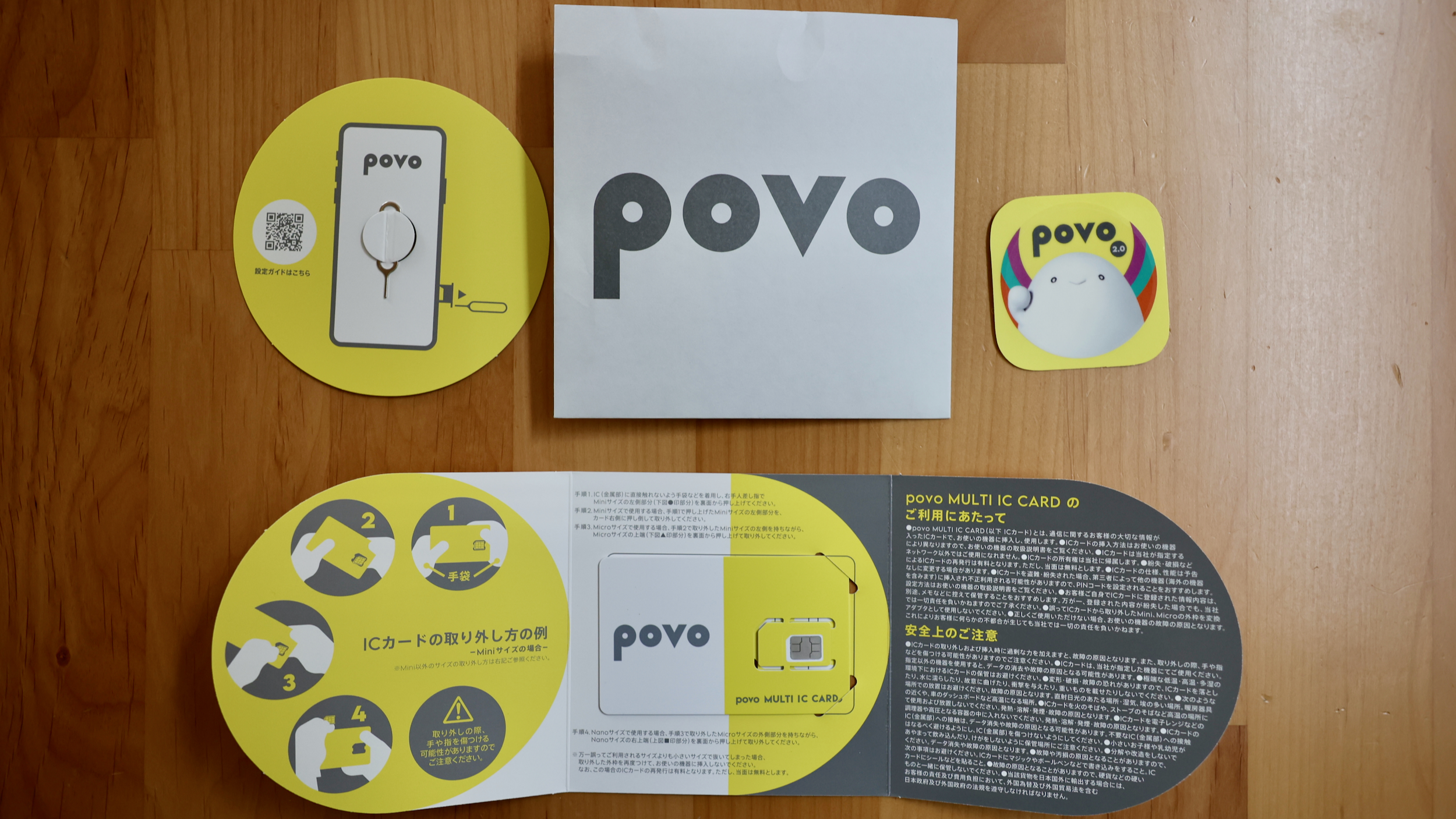- イントロダクション
- PART 1:現実を直視する(Choosing to choose)
- 第1章 なぜ、いつも時間に追われるのか
- 第2章 効率化ツールが逆効果になる理由
- 第3章 「時間がある」という前提を疑う
- 第4章 可能性を狭めると、自由になれる
- 第5章 注意力を自分の手に取り戻す
- 第6章 本当の敵は自分の内側にいる
- PART 2 幻想を手放すBeyond Control
- 第7章 時間と戦っても勝ち目はない
- 第8章 人生には「今」しか存在しない
- 第9章 失われた余暇を取り戻す
- 第10章 忙しさへの依存を手放す
- 第11章 留まることで見えてくるもの
- 第12章 時間をシェアすると豊かになれる
- 第13章 ちっぽけな自分を受け入れる
- 第14章 暗闇のなかで一歩を踏みだす
- 人生を生きはじめるための5つの質問
- エピローグ 僕たちに希望は必要ない
- 付録:有限性を受け入れるための10のツール
- 関連記事
イントロダクション
時間をうまく使うことが人の最重要課題になるはずだ。人生とは時間の使い方そのものだといってもいい。
世界は未知のものごとであふれているというのに、タイムマネジメントの先生たちときたら、目の前のつまらないタスクをこなすことばかり考えている。
本書は、時間をできるだけ有効に使うための本だ。ただし、いわゆるタイムマネジメントの本ではない。
生産性とは、罠なのだ。
PART 1:現実を直視する(Choosing to choose)
第1章 なぜ、いつも時間に追われるのか
時間を支配しようとする者は、結局は時間に支配されてしまうのだ。
今を犠牲にしつづけると、僕たちは大事なものを失ってしまう。
今を生きることができなくなり、未来のことしか考えられなくなるのだ。
つねに計画がうまくいくかどうかを心配し、何をやっているときも将来のためになるかどうかが頭をよぎる。いつでも効率ばかりを考えて、心が休まる暇はない。
本当はもっと重要で充実した時間の過ごし方があるんじゃないか。今こうやって黙々とこなしている仕事は、本来やるべきこととは違うんじゃないか。
この感覚はさまざまな形でやってくる。何か大きな目的のために自分を捧げたい。危機と苦しみに満ちたこの時代に、自分の力を労働や消費とは違うことに使いたい。こんな無意味な仕事を辞めて、自分の好きな仕事をしたい。限られた人生なのだから、もっと子どもと一緒に過ごしたい。自然の中で過ごしたい。とにかく通勤から解放されたい。
生産性を高めようとする努力が事態をかえって悪化させるのは、それが単なる現実逃避にすぎないからだ。
自分の時間は、あまりにも短い。その事実を直視するのは怖いことだ。
「我々は生活に必要な以上に熱心に、夢中で日々の仕事に取り組んでいる。立ち止まって考える暇ができては困るからだ。世の中がこれほど忙しいのは、誰もが自分自身から逃避しているためである」ニーチェ『反時代的考察』
自分には、限界がある。その事実を直視して受け入れれば、人生はもっと生産的で、楽しいものになるはずだ。
現実を直視することは、ほかの何よりも効果的な時間管理術だ。
大事なのは、意識的に選択することだ。何に集中し、何をやらないか。
もうひとつ大事なのが、「選択肢を確保する」という誘惑に負けないことだ。選択肢を増やすというのは、要するに困難な決断から逃げることにほかならない。
時間が限られているという事実を否定することなく、受け入れる。そのほうが、僕たちの人生はずっと充実したものになる。
第2章 効率化ツールが逆効果になる理由
やるべきことはいつだって多すぎるし、これから先もそれはきっと変わらない。そのなかで心の自由を得るための唯一の道は、「全部できる」という幻想を手放して、ひと握りの重要なことだけに集中することだ。
「もっと効率的にやれば忙しさから逃れられる」という希望を、あえて捨てればいいのだ。
第3章 「時間がある」という前提を疑う
ハイデガーの奇妙な視点から見れば、「自分は限られた時間である」というほうが正しい。限られた時間こそが、僕たちの存在の本質なのだ。
問うべき問題はひとつ。有限性に直面することを、自分が望むかどうかだ。ハイデガーにとっては、それこそが人間という存在の中心的課題だった。有限性が僕たちの人生を規定している以上、人が人として生きるためには、限られた生という事実を直視しないわけにはいかない。自分の限界をきっぱりと認めたうえで、ハイデガーが「死へ臨む存在」と呼ぶ醒めた意識で、可能な限り人生を生き抜かなくてはならない。
本当に病的なのは、ほとんどの人が普通だと思っていることのほうかもしれない。つまり、自分の有限性から目を背けハイデガー用語でいえば「頽落(たいらく)」した生き方をすることだ。
自分の有限性を直視して初めて、僕たちは本当の意味で、人生を生きはじめることができるのだ。
時々でもいい。存在することの驚きと、そのあまりの短さに思いを馳せてほしい。そうすれば、今ここで時間の流れのなかにいること(ハイデガー風にいうなら、時間の流れとして在ること)が、それまでとはがらりと変わって見えるはずだ。
そもそも、時間が少しでもあること自体が、不可解なほどに奇跡的なことなのだ。
第4章 可能性を狭めると、自由になれる
タスクを上手に減らす3つの原則
1. まず自分の取り分をとっておく
本当にやりたいことがあるなら、確実にそれをやり遂げるための唯一の方法は、今すぐに、それを実行することだ。
今やらなければ、時間はないのだ。
2. 「進行中」の仕事を制限する
何かを選ぶときには、他のすべてを捨てなければならない。でもそれを直視したおかげで、すべてを同時にこなすという選択肢はそもそも不可能なのだとシンプルに理解できた。
3. 優先度「中」を捨てる
優先順位が中くらいのタスクは、邪魔になるだけだ。
それらは人生のなかでさほど重要ではなく、それでいて、重要なことから目を逸らすくらいには魅力的だからだ。
第5章 注意力を自分の手に取り戻す
第6章 本当の敵は自分の内側にいる
自分は万能ではない。ただの魅力な人間で、それはどうしようもない。
そん事実を受け入れたとき、苦しみはふいに軽くなり、地に足のついた解放感が得られるだろう。「現実は思い通りにならない」ということを本当に理解したとき、現実のさまざま制約は、いつのまにか苦にならなくなっているはずだ。
PART 2 幻想を手放すBeyond Control
第7章 時間と戦っても勝ち目はない
「人の存在とは一瞬の時間の連続である」ハイデガー
今この瞬間だけが、僕たちに関係のある唯一の時間だからだ。
未来をコントロールしたいという執着を手放そうということだ。そうすれば不安から解放され、本当に存在する唯一の瞬間を生きられる。つまり、今を生きることが可能になる。
第8章 人生には「今」しか存在しない
実際、人生のあらゆる瞬間はある意味で「最後の瞬間」だ。
今を生きるための最善のアプローチは、今に集中しようと努力することではない。むしろ「自分は今ここにいる」という事実に気づくことだ。
今を生きるとは、今ここから逃れられないという事実を、ただ静かに受け入れることなのかもしれない。
第9章 失われた余暇を取り戻す
余暇を有意義に過ごそうとすると、余暇が義務みたいになってくる。
もう余暇すらも、やることリストのひとつになってしまったからだ。
現代に生きる僕たちは、休みを「有意義に使う」とか「無駄にする」という奇妙な考えにすっかり染まっている。
でも本当は、余暇を「無駄に」過ごすことこそ、余暇を無駄にしないための唯一の方法ではないだろうか。
何の役にも立たないことに時間を使い、その体験を純粋に楽しむこと。
一度きりの人生を存分に生きるためには、将来に向けた学びや鍛錬をいったん忘れる時間が必要だ。怠けることは単に許容されるだけではなく、人としての責任だといっていい。
第10章 忙しさへの依存を手放す
焦って運転すると結果的に時間がかかることは、交通に関する研究ですでに明らかになっている。
現実のスピードをどんどん速めたいという欲望は、人々の読書体験にもはっきりと現れている。
時間をコントロールしたいという僕たちの傲慢さを、読書は許してくれない。無理に急いで読もうとしても、意味がすり抜けていくだけだ。
何かをきちんと読むためには、それに必要なだけの時間がかかる。
自分の無力さを認めて、不可能を可能にしようとする無駄な試みを放棄したとき、人は実際に可能なことに取り組むことができる。まず現実を直視し、それからゆっくりと、より生産的で充実した生き方に向けて歩みだすのだ。
幻想を捨ててほっと息をつき、ありのままの現実を醒めた目で見つめよう。そのときあなたは、ちょっと古くさいけれど何より重要な能力を獲得しはじめるだろう。
「忍耐」という力だ。
第11章 留まることで見えてくるもの
忍耐を身につける3つのルール
1.「問題がある」状態を楽しむ
「すべての問題を解決済みにする」という達成不可能な目標を諦めよう。そうすれば、人生とは一つひとつの問題に取り組み、それぞれに必要な時間をかけるプロセスであるという事実に気づくはずだ。
2. 小さな行動を着実に繰り返す
もっとも生産的で成功している学者たちは、1日のうち執筆に割く時間が「少ない」という意外な事実が明らかになった。ほんの少しの量を、毎日続けていたのだ。
適切なペースをつかむためのコツは、1日に割り当てた時間が終わったら、すぐに手を止めて立ち上がることだ。
途中で思いきってやめることで、忍耐の筋肉が鍛えられ、何度もプロジェクトに戻ってくることができる。そのほうが長期的に見れば、ずっと高い生産性を維持できるのだ。
3. オリジナルは模倣から生まれる
クリエイティブな仕事に限った話ではない。人生のさまざまな局面で、僕たちは選択を迫られる。しかし、平凡な道が平凡に終わるわけではない。辛抱強くみんなと同じ道を歩んできた人だけがたどり着ける、豊かで独創的な境地というものもある。
かけがえのない成果を手に入れるには、たっぷりと時間をかけることが必要なのだ。
第12章 時間をシェアすると豊かになれる
「デジタルノマド」が誤った呼び方であることは知っておいたほうがいい。
本来のノマド(遊牧民)は、孤独な放浪者ではなく、集団行動を重視する人たちだった。どちらかというと、定住民よりもノマドのほうが個人の自由度は低かった。
個人の時間的な自由度が高まると、必然的に、自分の時間と他人の時間を合わせることが難しくなる。
通勤が減って働く時間と場所を自由に選べるようになると、仕事を通じて人とのつながりを築くことが難しくなる。
個人主義的な時間に対抗して、少しだけ共同の時間を取り戻してみてはどうだろう。
第13章 ちっぽけな自分を受け入れる
「宇宙的無意味療法」やるべきことが大きすぎて圧倒されるとき、少しだけズームアウトしてみれば、すべてはちっぽけな問題に見えてくる。ほとんど無だ。「宇宙はあんたのことなんかクソほども気にしていない」
非現実的なハードルから解放されたとき、限りある時間を有意義に使う方法は、今までよりもずっと多様な可能性に開かれる。今やっていることのなかに、思ったよりもずっと意味のあることがたくさんみつかるかもしれない。今までくだらないと思っていたことが、本当はとても価値のあることだと気づくかもしれない。
どんな仕事であれ、それが誰かの状況を少しでも良くするのであれば、人生を費やす価値はある。
宇宙的無意味療法は、この壮大な世界における自分のちっぽけさを直視し、受け入れるための招待状だ。
4000週間というすばらしい贈り物を堪能することは、偉業を成し遂げることを意味しない。
むしろ、その逆だ。
自分に与えられた時間をそのまま味わったほうがいい。
人生を、ありのままに体験しよう。
第14章 暗闇のなかで一歩を踏みだす
時間を支配しようとする態度こそ、僕たちが時間に苦しめられる原因である。
僕たちが交通渋滞に文句を言い、幼児がさっさと動いてくれなくてイライラするのは、自分がスケジュールに対してあまりにも無力である事実を認めたくないからだ。
そんなつらい現実を受け入れて、何の得があるのかって?
ここにいることができる。
人生の本番を生きられる。限られた時間を、本当に大事なことをして過ごせる。今この瞬間に集中できる。
痛みが必然であることを受け入れれば、自由がやってくる。ようやく人生を生きられるようになる。
人生を生きはじめるための5つの質問
質問1:生活や仕事のなかで、ちょっとした不快に耐えるのがいやで、楽なほうに逃げている部分はないか?
「この選択は自分を小さくするか、大きくするか?」と自問する。
たとえば、今の仕事を辞めるか悩んでいるとしよう。そんなとき「どうするのが幸せだろうか」と考えると、楽な道に流されるか、決められずにずるずるひきずってしまう。
一方、その仕事を続けることが人間的成長につながるか(大きくなれるか)、それとも続けるほどに魂がしなびていくか(小さくなるか)と考えれば答えは自然と明らかになるはずだ。
できるなら、快適な衰退よりも不快な成長をめざしたほうがいい。
質問2:達成不可能なほど高い基準で自分の生産性やパフォーマンスを判断していないか?
質問3:ありのままの自分ではなく「あるべき自分」に縛られているのは、どんな部分だろうか?
自分が楽しいと思えることが、最善の時間の使い方かもしれない。
質問4:まだ自信がないからと、尻込みしている分野は何か?
質問5:もしも行動の結果を気にしなくてよかったら、どんなふうに日々を過ごしたいか?
ユングにいわせれば、個人の人生とは「みずから切り拓いていく道であり、誰も通ったことのない道」である。
「ただ静かに、目の前のやるべきことをやりなさい。(中略)次にすべきこと、もっとも必要なことを確信をもって実行すれば、それはいつでも意味のあることであり、運命に意図された行動なのです」
どれだけ多くの人を助けたか、どれだけの偉業を成しとげたか、そんなことは問題ではない。時間をうまく使ったといえる唯一の基準は、自分に与えられた時間をしっかりと生き、限られた時間と能力のなかで、やれることをやったかどうかだ。
どんな壮大なプロジェクトだろうと、ちっぽけな趣味だろうと、関係ない。
大事なのは、あなただけの次の一歩を踏み出すことだ。
エピローグ 僕たちに希望は必要ない
そう、世界はすでに壊れている。そしてあなたの人生も同じだ。望んでいた完璧さや安心なんて、最初からどこにもなかったのだ。
あなたの4000週間は、不完全なまま、いつだってすでに尽きかけている。
この不愉快な現実は、しかし、自由への一歩だ。
人の平均寿命は短い。ものすごく、バカみたいに短い。
でもそれは、絶望しつづける理由にはならない。限られた時間を有効に使わなくてはとパニックになる必要もない。
むしろ、安心してほしい。
到達不可能な理想を、ようやく捨てることができるのだから。どこまでも効率的で、万能で、傷つくことがなく、完璧に自立した人間になることなど、はじめから無理だったと認めていいのだから。
さあ腕まくりをして、自分にできることに取りかかろう。
付録:有限性を受け入れるための10のツール
- 「開放」と「固定」のリストをつくる
- 先延ばし状態に耐える
- 失敗すべきことを決める
- できなかったことではなく、できたことを意識する
- 配慮の対象を決める
- 退屈で、機能の少ないデバイスを使う
- ありふれたものに新しさを見いだす
- 人間関係に好奇心を取り入れる
- 親切の反射神経を身につける
- 何もしない練習をする
何もしないことができる人は、自分の時間を自分のために使える人だ。現実逃避のために何かをするのは、もうやめよう。
心を落ち着かせ、自分だけの限られた時間を、じっくりと味わおう。