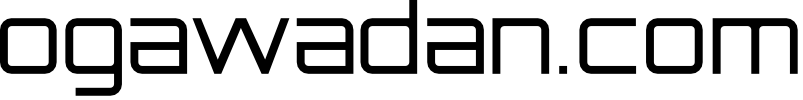バルザック著『ゴリオ爺さん』(フランス1835年刊)は「二人の娘への盲目的父性愛の悲劇」などと解説される。しかし読み終わってみると、むしろこの作品で描かれているのは単なる父性愛ではなく、母親のいない娘に対する父親の母性愛であり、悲劇ではなく喜劇であるように思える。
つまり、ゴリオ爺さんという存在は、なき母親の存在を埋める父親兼母親であり、また悲劇的ではあるが喜劇的にも映る、なんとも両義的な人物である。
『ゴリオ爺さん』には男性的、父性的なもの、娘的な物があふれている一方で、母子関係を軸とする人物は徹底的に省かれている不思議さがある。ゴリオ爺さんの父性はその不在の母性を埋め合わせるために必要なものであり、母性を父性で補おうとすればするほど、父性だけが過剰どころか異常なほど肥大する。
バルザックがゴリオ爺さんに託したのは、偏った人間関係のなかで均衡を取ろうとする人間たちの悲劇/喜劇だったかもしれない。極めて世俗的な世間で理想の親子関係を夢見たゴリオ爺さんが味わう幻滅の結末。
また、父親の恩を無碍にする二人の娘は残酷であるが、それは一方で異常なほどの献身をみせる父親への「わずらわしさ」や「面倒くささ」の現れともとれる。登場人物の誰かを断罪したくてもできない巧妙な人物造形がうかがえる。
『ゴリオ爺さん』はバルザックの人間喜劇の中心となる長編であり、数々の登場人物が躍動するが、どの人物も多面的に人間性が描かれているため、誰か一人を気に入ったり、反対に嫌悪したりすることは難しい。
ゴリオ爺さんと同じ下宿に住むヴォートランとラスティニャックも非常に強烈な個性を放つ。
ラスティニャックが罪人ヴォートランを評するその言葉に社会構造が現れている。
「ヴォートランのほうがずっと偉い。彼は《服従》と《闘争》と《反抗》という、社会を表現する三つの大きな要素を見きわめていた。つまり《家族》と《世間》と《ヴォートラン》だ」それでいて彼は、態度を決めかねていた。《服従》は退屈であり、《反抗》は不可能で、《闘争》はあやふやなのだ。彼の思念は、ひとりでに彼を家族のもとへ連れ戻した。彼はあの静かな生活の清らかな感動を思い出し、自分をいつくしんでくれた人びとの間ですごした日々を回想した。家庭というものの自然の 掟 を忠実に守って、そのなつかしい人びとは、そこに充実した、間断のない、そして何の苦悩もない幸福を見いだしているのだ。
『ゴリオ爺さん』は前半は説明的にゆっくりと立ち上がり、後半からゴリオ爺さんの死までの流れが早くなる部分が面白かった。
関連記事